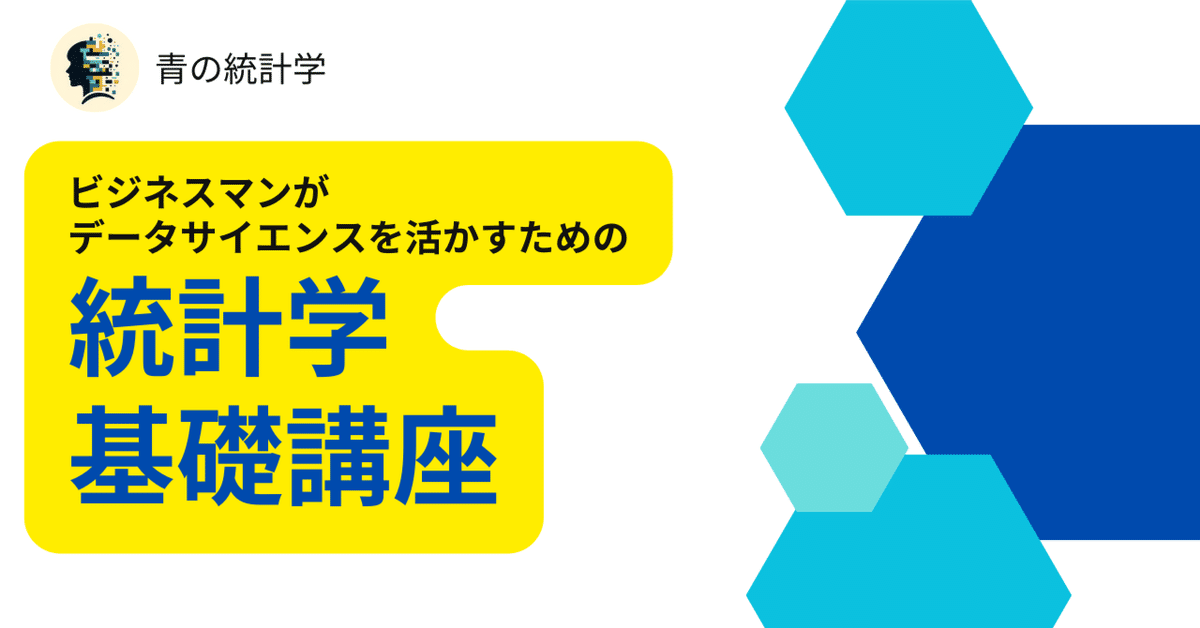UI/UX 改善における統計的アプローチ: ~サンプリング設計とベイズ推論の活用~
1. UI/UX 改善と統計学の関係
ユーザーの操作感やインタラクションをより快適にするためのUI/UX改善は、データドリブンなアプローチができるようになってます。
たとえば「新しいボタン配置Aが既存配置Bよりもコンバージョン率を上げられるか?」といった疑問を検証するために、A/Bテストを実施するケースは多いでしょう。こうした実験を設計・解析するうえで統計学を使っていきます
とりわけ「帰無仮説検定」をベースにした頻度主義統計学と「事前分布」「事後分布」で推論を進めるベイズ統計学が対照的に語られますね。今回は、UI/UX 改善における実験デザインやサンプリングの途中変更がどのように扱われるかを中心に深掘りしていきます!
2. A/Bテストにおける帰無仮説検定
2.1 基本的な仕組み
頻度主義統計学に基づくA/Bテストでは、まず「帰無仮説 ${H_0}$」を設定します。たとえば、
- ${H_0}$:新デザインAが既存デザインBに対して指標(コンバージョン率など)で差がない
- 対立仮説 ${H_1}$:AがBより優れている
このとき、一定のサンプルサイズ ${N}$ を事前に決め、両デザインをランダムにユーザーに割り振って指標を計測し、有意水準 ${\alpha}$(しばしば0.05)に基づいて「差がある」と言えるかどうかを判定します。
たとえば、Aの平均コンバージョン率を ${\bar{X}_A}$、Bを${\bar{X}_B}$、それぞれの母分散を ${\sigma^2}$(仮定)とし、A/Bテストで均等割り当ての場合は各群のサイズが ${N/2}$ とすると、検定統計量は
$${Z = \frac{\bar{X}_A – \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{N/2} + \frac{\sigma^2}{N/2}}} = \frac{\bar{X}_A – \bar{X}_B}{\sigma \sqrt{\frac{2}{N/2}}} = \frac{\bar{X}_A – \bar{X}_B}{\sigma \sqrt{\frac{4}{N}}}}$$
これが正規近似できるとすれば、
$${p\text{-value} = P(Z_{\text{標準正規}} \ge z_{\text{obs}})}$$
のようにして帰無仮説を棄却するかどうかが決まります。
2.2 途中でのサンプリング変更がもたらす問題
本来、頻度主義統計学では「サンプルサイズを事前に固定する」ことが前提になっています。もし実験途中で結果を見て「まだ有意性が出ていないから、さらにデータを集めよう」といったやり方を繰り返すと、有意水準 ${\alpha}$が守られなくなる可能性が高まります。

言い換えれば、いずれ有意になるまで検定を続ければ、実質的に何らかの差が“ある”という結論を得やすくなってしまうのです。
途中で結果を見て「まだ有意にならないからもっとデータを集めよう」ということを繰り返すと、実質的に有意水準が「どんどんリセット」されるような状態になり、最終的に有意差を発見しやすくなってしまいます。
そのため、上記の枠組みでは「事前に ${n}$ を固定しないサンプルサイズの追加」は不適切な行為とみなされることがあります。
ただし、途中解析やサンプルサイズの動的変更がどうしても必要な場合があり、その際には中間解析用の補正(たとえば複数回の解析を行う場合のペナルティ)や逐次分析の手法を設計段階で導入することで、頻度主義統計学でも「途中で見ても不正にはならない」を構築できます。
詳しくはこのあたりが参考になります。
3. ベイズ推論と動的実験デザイン
3.1 事後分布の逐次更新
ベイズ推論は、未知パラメータ ${\theta}$(たとえば「新デザインAの平均コンバージョン率」など)を事前分布 ${p(\theta)}$ で表し、観測データ ${D}$ が得られた後に
$${p(\theta \mid D) = \frac{p(D \mid \theta)\,p(\theta)}{p(D)}}$$
によって事後分布を計算し、パラメータに関する不確実性を更新していきます。A/Bテストでもベイズ推論を採用すると、毎回ユーザーからデータを得るたびに「AとBのどちらがより優れているか」という信念度合いをアップデートできるわけです。
3.2 UI/UX 改善での応用:途中打ち切りとアダプティブサンプリング
UI/UX 改善だと、実験途中でAデザインがBより明らかに優位だと示唆されたら、その時点でAを正式版として導入し、実験を終了してしまうのも戦略の一つです。

心理物理測定や医療分野の臨床試験で広く利用されているアダプティブ実験計画ですね。
このような動的サンプリングは、ベイズ推論の根幹である「尤度原理」を満たしているため、あらかじめルールを定めておけば、実験を途中打ち切りしても分析の整合性は保たれます。
大まかに言えば「得られたデータの内容(どのデザインにどれだけのユーザーが割り当てられて、どれぐらい成功したか)こそが本質的に大事であり、“どういう過程でサンプル数を増やしたか” は推論の正しさには影響しない」という考え方です。
したがって、事前に『サンプルを何件集める』と厳密に決めていなくても、データが入り次第、事後分布をアップデートして「そろそろAデザインがBデザインを上回っている確率が十分高い」となれば、その時点で打ち切りをしても問題ないわけです。
3.3現場観点で語ってみる
この「途中打ち切りをしても整合性が崩れない」メリットは、UI/UX改善のプロジェクトで「なるべく早く有効なデザインを確定し、開発・運用リソースを別の改善に回したい」という場面で生きてきます。
たとえば、もし新しいデザインAが圧倒的に良いという事後確率が高くなったら、実験を早々に終了してAに切り替え、いわゆる「勝ち案件」として振り切り、残りの時間を別の施策に振り向けることができます。
逆に「差がなかなか出ない」ときでも、ベイズ推論なら逐次的に“不確実性”を定量化できるため、「あともう少しデータを集めないと判断が難しい」という場合にも適切な追加サンプリング量を見積もりやすくなります。

「データが入るごとに自然に事後分布を更新していく」という方法論のほうが、実務上の自由度と整合性の両立がしやすいのも事実です。
4. 例:ベイズ的推定プロセス
簡単な例として、新デザインAの平均コンバージョン率 ${\mu}$ を正規分布で仮定し、事前分布を
$${\mu \sim \mathcal{N}(\mu_0, \tau^2)}$$
とします。もしユーザー行動から観測したデータが${\{x_i\}_{i=1}^N}$で、これが母分散 ${\sigma^2}$ 既知の正規分布に従うと仮定できれば、事後分布は同じく正規分布になり、
$${\mu \mid x_1, \ldots, x_N \sim \mathcal{N}\!\Bigl( \frac{\sigma^2 \mu_0 + N \tau^2 \bar{x}}{\sigma^2 + N \tau^2},\; \frac{\sigma^2 \tau^2}{\sigma^2 + N \tau^2} \Bigr)}$$
で表されます。 ${\bar{x}}$ は観測データの平均です。
データが1点ずつ追加されるたびに ${\bar{x}}$ と ${N}$ を更新すれば、事後分布が逐次アップデートされていくという仕組みになります。
UI/UX の実験でも、得られるユーザー反応を都度反映して確信度が十分高まった段階で実験を打ち切るなど、動的サンプリングが自然に導入できます。
5. まとめ!
UI/UX 改善の現場で、検証設計する際は、「サンプルサイズを変えることが不正かどうか」を気にするよりも「最初に定めた手順や解析計画と矛盾しないか」を確認することが重要です。
「統計学の不正」と言われるのは、典型的に帰無仮説検定を行う前提で有意水準 ${\alpha}$ を保ったまま途中で追加サンプリングを行い、${p}$値が有意になるまで繰り返すようなケースです。ベイズ推論の場合は観測のたびに事後分布を更新していくので、結果に応じてサンプリングを増減させることは自然な手続きです。
青の統計学は、東京大学を卒業後、事業会社でデータサイエンティストとして勤務する筆者が運営する、AI・データサイエンスの総合学習メディアです。 自身の大学時代の経験から、教科書だと分かりにくかった事項を克服でき、かつ実務で活かせる知識を楽しく学べるように、インタラクティブ学習ツール「DS Playground」を開発しており、大学での講義の材料としても利用されています。Xフォロワー1万人を突破!