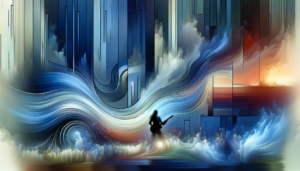【論文解説】リンパ節ごとのレパトア解析(4)
(4)では、resultの後半部分、T細胞の移入実験を解説します。
この記事では、以下の論文を紹介しています。
Stephanie K. Lathrop, Nicole A. Santacruz, Dominic Pham, Jingqin Luo, Chyi-Song Hsieh;Antigen-specific peripheral shaping of the natural regulatory T cell population J Exp Med 22 December 2008; 205 (13): 3105–3117. doi: https://doi.org/10.1084/jem.20081359
論文の紹介とabstractの解説を載せた(1)
https://statisticsschool.com/?p=718
introductionの解説(2)
https://statisticsschool.com/?p=760
resultの前半部分、リンパ節ごとのレパトア解析の解説(3)
https://statisticsschool.com/?p=1110
T細胞移入の実験系
実験の目的は、(3)の最後でも述べたように、
「末梢でのTreg⇄Tconvの変換はレパトア全体にどれくらい寄与しているのかをより直接的に示す」ことです。
そのために、マウス体内にT細胞を注射して、それがどう変化するのかをみていきます。
1:Tregがほんの少し混ざったTconvを移入
Tregのみ、またはTconvのみを移入すると、生体内に元々あったTregとTconvのバランスを崩してしまいかねないため、
TregとTconvが混ざった状態で移入を行いました。
Tregの方が増殖が速いという先行研究をもとに、実際のマウス体内におけるTregの割合よりも、移入細胞中のTregの割合は低くしてあります。
移入した細胞は、Tconvが1 x10^7 cells, Tregが1~2 x10^7 cellsです。
私の個人的な感覚として、末梢のリンパ節全体からは大体1 x10^9 cellsくらい取れるので、
元々体にあった1%くらいの量のT細胞を体の中に突っ込んだ感じになります。結構入れたんですね〜
2:純粋なTregだけ、Tconvだけを取ってくるために、Foxp3-gfpマウスを使用
このマウスは、Tregだけが発現しているFoxp3の下流にgfpを遺伝子導入したもので、gfpの蛍光によってTregを取ってくるようにしたものです。
Foxp3は転写因子なので、核内にしか存在しません。
転写因子の仕事は、核内にあるDNAに結合することで遺伝子発現を変化させることなので、核の中にしかいないのです。
Foxp3の発現を見るためには核内染色と言って、細胞膜に穴を開けて核内まで抗体が入り込めるようにする必要がありますが、
それをすると細胞が小さくなってしまい、セルソーター(細胞を種類ごとに分ける機械)によって分けられなくなってしまいます。
そのため、Foxp3の発現の有無で細胞をソートするには、このような遺伝子操作が必要になってきます。
3:移入した細胞に含まれるTregとTconvが区別できるようになっている
ここではCD45.1という遺伝子型を持ったマウスから取ったTregを、CD45.2という遺伝的背景を持ったマウスから取ったTconvに混ぜています。
CD45.1とCD45.2は、持っている遺伝子配列が異なっているだけで、機能には全く影響を及ぼしません。このような関係を(ざっくりと)アイソフォームと言います。
CD〇〇は細胞の表面分子の識別名ですが、マウスの遺伝子型や系統名としてはLy5.1やLy5.2とも言われます。
そのおかげで、マウスに細胞を移入する時などに、入れた細胞と、マウスが元々持っていた細胞とを区別するのによく使われます。
4:入れた細胞と、マウスに元々あったT細胞が区別できるようになっている
TregとTconvの区別と同様に、移入細胞とドナーの細胞も、遺伝子型によって区別されています。
先ほどとは別の表面分子、CD90.1とCD90.2というアイソフォームを利用しています。
Thy1.1やThy1.2という別名もあります。このおかげで、移入細胞の変換だけを観察することができます。
5:移入から3~4 週間後に、リンパ節と脾臓の細胞を全てプールして解析を行なった
結果
解析時にTregとして存在していた移入細胞は、ドナーに元々あったTregと似た表現型を持つ
Tregの定義に使われるFoxp3以外のタンパク質の発現量を調べると、
CD25(サイトカインIL-2の受容体)とGITR(Tregの増殖やエフェクター機能を調節するスイッチのような分子)の発現量が高くなっていました。
これは一般にTregで見られる特徴です。
筆者達は、体外から入れ込んだ細胞由来のTregであっても、普通のTregのような挙動を示していると言いたいんだと思います。
末梢において、Treg→Tconvの変換は頻繁には起こらない
移入時に0.001%程度しか入っていなかったTregは、増殖が速いとは言え、解析時にも0.3%程度しか存在していませんでした。
Tregのうち、移入した時からTregで、Tregの状態を維持していたものはそのうち2.1%であり、他は移入時にはTconvだったものがTregに変化したものでした。
つまり末梢で起こったTconvからTregへの変換は、たったの0.3%程度であり、レパトア全体に大きな影響を及ぼすほどではない、ということがわかりました。
末梢でのTreg⇄Tconvの変換は腸間膜リンパ節で頻繁に起こっている
筆者らは、先行研究で既に示唆されていたことの再現を取りました。
先程のデータは末梢のリンパ組織全てを一緒くたにして、移入細胞中のTregの割合を調べていましたが、
脾臓/腸間膜リンパ節/その他の皮膚所属リンパ節に分けて同じ解析を行ってみました。
すると、腸間膜リンパ節だけ移入細胞中のTregの割合が他の2倍近く、約0.5%に達しており、
脾臓や皮膚所属リンパ節では0.2%近い、という結果になりました。
つまり、先程の結果はリンパ節ごとの違いを押し並べて測った、平均的な値であった、ということがわかりました。
胸腺のTconvを移入してもTregへの変化はあまり起こらない
予想に反してTreg⇄Tconvの変換があまり見られなかったことに対して、筆者らはこのように考えました。
「移入した細胞の中には、既にTreg⇄Tconvの変換が起こっているものがあり、
そのような細胞は、実際には変換を起こしている細胞ではあるものの、移入前後の変化には現れない。
末梢に行く前の細胞を使用すれば、末梢で起こる変化全てを検出できるのではないか?」
そこで筆者らは、胸腺で分化を終え、末梢に移行できる状態になった細胞を代わりに移入してみました。
このように成熟した状態のT細胞は、CD24の発現量が低いことと、CD62Lの発現量が多いことで定義されています。
この実験系ではTconvのみを移入しています。
結果、胸腺細胞だと0.8%のTconvがTregになっていました。
Tregの中の割合で言うと4~7%であり、結局大きな割合を占めてはいないと分かりました。
T細胞のいないマウスに移入したTconvでは、Tregへの変化が頻繁に起こる
予想に反してTreg⇄Tconvの変換があまり見られなかったことに対して、筆者らはもう一つの仮説を立てました。
「細胞を移入されたマウスに既に存在していたTregが、移入細胞におけるTreg⇄Tconvの変換を邪魔したのではないか?」
そこで筆者らは、遺伝子改変によってT細胞が体内に存在しなくなったマウスにTconvを移入しました。
TCRのβ鎖をコードする遺伝子をノックアウト(遺伝子操作により欠落させる)ことにより、 T細胞がいないマウスを作製しています。
移入したT細胞のTCRは、今後のレパトア解析を見据えてβ鎖を1種類に固定したものにしました。
この実験でもTconvのみを移入しています。
結果、先ほどよりも高い割合のTconvがTregへと変化したことが分かりました。
既にTregがいて、充分に機能している場合は変換が起こりにくく、Tregが全くいない状況では変換が起こっている、というのは極めて自然な現象です。
バランスを取るような力が働いているイメージです。空いているニッチを埋める、という風によく言われます。
まあ移入細胞の実験系では、TconvのTregへの変換と増殖を区別することができないと言うデメリットはあります。
たくさんの種類のTconvが均等にTregになったのか、数種類のTconvがTregになった後、増殖して数を増やしたのかが区別できません。
この2つの結果を区別する手段の一つがレパトア解析というわけです。
T細胞のいないマウスに移入したTconvでは、Tregの頻度分布が異なる
T細胞のいない環境で生まれたTregは、生体内にいるTregと似たような表現型を持っていました。
先程述べたCD25とGITRの他に、CD103(組織常在性Tregのマーカー?細胞接着分子インテグリンの一種)の発現も高いことが分かりました。
しかし、リンパ節ごとにTregの割合を調べると、腸間膜リンパ節でのTregの割合だけが低いということが分かりました。
T細胞が正常に存在するマウスに移入した時は、腸間膜リンパ節だけでTregの割合が高かったので、これは正反対の結果になります。
この現象のメカニズムとして、筆者らは、Tconvが既に腸間膜リンパ節に沢山存在していることを考察しています。
T細胞のいないマウスにTconvを移入すると大腸炎が起こることがわかっています。
Tregへの変換が起こるよりも前に、Tconvが腸内にある無害な抗原に対して反応し、活性化することによって自己組織を傷つけるため、
大腸炎が生じていると考えられます。
末梢でTregになった細胞のレパトアと、TregにならずTconvのままだった細胞のレパトアは異なる
頻度の高い順に50個のTCR配列を抜き出し、両者で頻度を比較すると、頻度が大きく異なっている事が分かりました。
そもそも片方にしか存在しないTCR配列も比較的多くありました。
ちなみに、2つのレパトアに含まれるTCR配列があまり被っていないような状態はoverlapが少ない、と表現されます。
確かに、新たに生じたTregとTconvでMorisita-Horn similarity indexを算出し、レパトア同士の類似度を評価しても、
値は低くレパトアは似ていないという結果が出ています。
もし、移入したTconvのうちランダムにTregが生じるなら、TCR配列は関係ないということになるので、
overlapはもっと大きくなり、その頻度も近いものになるはずです。
つまり、Tregに変化しやすいTconvと、変化しにくいTconvがいて、その違いはTCR配列に起因している可能性がある、ということです。
あるマウスから得られた細胞を複数のマウスに移入しても、異なるTregやTconvのレパトアが形成される。
1匹のマウスから得られたTconvを複数のT細胞欠損マウスに移入し、それぞれで形成されたレパトアはどのように異なるのかを検証しました。
Treg同士、Tconv同士でMorisita-Horn indexを算出すると、低い組み合わせや高い組み合わせが存在しました。
低い場合は、同じ個体の中のTregとTconvのsimilarityと同じくらいに低く、高い場合は0.5程度でした。
TregになるかどうかはTCRに依存するけれども、そのうちどれが増殖するのかは、そのマウスが出会う抗原やその量に依存します。
個体差に起因するTCR配列の頻度の違いが、類似度の低下につながったのだと筆者らは考えています。
つまり、たまたま同じTCR配列を持つ細胞が増殖すれば、類似度も上がります。
similarityが低い組み合わせも高い組み合わせも存在するのは、このようなメカニズムを考えるとしっくり来ます。
ここまでで、末梢で起こるTconvのTregへの変化はランダムではなく、そのTCRに何らかの傾向がある事がわかったので、
つぎに筆者らは、具体的にどのような傾向があるのかを掴むことによって、Treg変化のメカニズムに迫ろうとしました。
「Tregに変化するTconv」のTCR配列は、TregのレパトアにもTconvのレパトアにも存在する
元々両方に存在するTCRなら、TconvがTregになったところでレパトア全体が大きく変化しないのも納得できます。
TregになるかTconvになるかは、TCR配列によって決まっている、という考え方があります。
末梢で誘導される(Tconvから変化する)Tregは、元々TregになるようなTCRを持っていましたが、
胸腺では自己抗原に出会えなかったからTregになれずにTconvとして分化した。
その後末梢へと移行し、腸などで、胸腺では出会わなかった抗原と出会ってTregになった、という仮説です。
この仮説に基づけば、末梢で誘導されたTregのTCRは胸腺のTregのレパトアには存在しないはずです。
しかし、予想に反して、胸腺Tregのレパトアには、末梢でTregになったTCR配列、しかも頻度が高いものが存在していました。
一方、頻度が比較的低いものは胸腺に存在していませんでした。
筆者らは、末梢で生じたTregが、全身を循環する際に胸腺にも入ってしまうために、胸腺でも見つかったのだと考察しています。
このさらなる仮説を確かめるために、筆者らは末梢のCD4T細胞を移入し、胸腺まで循環するかどうかを見ました。
結果、胸腺で見られるTregの4%程度が末梢から再循環してきた細胞由来のものだと分かりましたが、これだけでは説明できません。
そこで筆者らは、「いくつかのTCRは、胸腺でもTregになれるし、末梢でもTregになる事ができる」という仮説を立てました。
胸腺でTregになれなかったT細胞が、末梢でTregになるチャンスを再び与えられる、といったイメージです。
胸腺でのTregの誘導が不完全で、末梢での誘導がこれを補っている、というメカニズムが考えられます。
この論文では、実際にどのようにして補っているのかまでは示していません。
「TregかTconvかは、TCR配列(clone)によって決定されているのではないか?
しかし胸腺でのTregへの分化誘導は不完全で、本来TregになるはずだったT細胞が、Foxp3を発現する前に末梢に移動してしまう事がある。
そのようなTconvが末梢でTregに変化しているのではないか?」という予測までです。
長くなりましたがこの論文に関しては大体紹介できたかなと思います。
次回はCNS3というDNA上の転写調節領域と、レパトアの関係を調べた論文を紹介します。